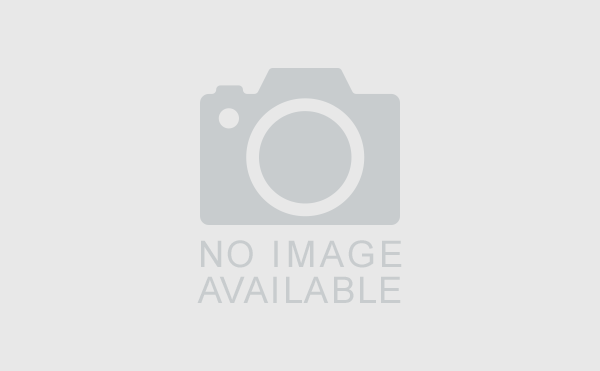鹿革を草木染めで製品化 食害対策で捕獲の鹿を有効活用
<記事要約>
天城高原で食害対策として捕獲された鹿の革を、障害児就労支援施設「ひかり工房」(伊東市川奈)が草木染にして製品化した。「ひかり工房」は2017年から伊豆半島で採取した植物による繊維染色に取り組み、2019年に独自ブランド「ひかりいろ」を立ち上げている。
今まで捕獲した鹿の革が廃棄されていた事を聞き、製品化に挑戦。当初は市販の鹿革で試したが思い通りの色を出せなかった。最終的に兵庫県姫路市の業者が日本古来の技法「白なめし」でなめした革を試したところ、鮮やかに発色した。
現在9色ある鹿革のうち4色は、生産工程で化学物質を使わず日本皮革産業連合会が定める日本エコレザー基準の最高ランクに認定されている。
製品は一枚革だけでなく、名刺入れ、キーケースなども展開する。今月24日・25日、都内で開かれるレザーワールドに出店する予定。
<捕獲した鹿の現状>
現在、伊豆半島と富士地域の推定生息数は約5万頭。2019年度は市町所管と狩猟を合わせて、約2万2千頭を捕獲した。しかし捕獲後の有効活用は難しく、昨年度、県が管理捕獲した約1万頭のうち、食肉などに加工されたのは約5500頭にとどまる。残りは埋設処理など。
捕獲後、なるはやで処理をしないと製品化するのが難しい鹿。捕獲場所からの輸送もままならず、その場で埋める、っていう場合も多いみたいですね。昨年の県の管理捕獲でも、埋設処理などが約45%を占めてます。
処理施設に一番搬入しやすいのが、車ではねた個体、なんていうのも聞きます(猟だと道路まで運ぶのが大変)。
まずは処理施設に搬入されないと始まらない、鹿の有効活用。
処理施設で食肉やペットフード、動物園むけの餌などとして食べられる部分が取られて、残るのが革や角。
昔、イズシカ(伊豆市の鹿対策事業)では角を使って、ナイフの柄を作ってるとか聞いたような気もしますが、革を活用する話は聞かなかったですね。今回の記事の伊東市の場合も、食肉処理したあとの革はこれまで廃棄されていた。
理由は毛皮需要の低迷、あとは革をなめすのが大変っていうところでしょうか。
「ひかり工房」さんの場合も、理想的な革のなめしかたに行き着くまでに結構な数の試行錯誤があったみたい。
なにはともあれ、せっかく捕獲した鹿をムダにせずに有効活用できる取り組みがひろがるといいですね。
 |
 |
 |