サクラエビ秋漁 今年も不漁か
サクラエビ秋漁前調査 魚影薄く小型目立つ 依然、状態改善せず
<記事要約>
静岡県の水産・海洋技術研究所と桜えび漁業組合が10月1日までに、駿河湾全域で断続的に実施した漁獲可能な親エビの体長組成などの資源状態の調査で、沿岸部の魚影は薄く、サンプル採取したエビも小型の個体が多かった。年々厳しさを増す桜えびの資源状態は改善が見られない。
県水産技術研究所は今後サンプルを分析して、10月19日に由比港漁協で開催される漁業者や加工業者、学識経験者などが参加する情報連絡会で結果を報告する予定。
11月1日に解禁され12月23日までが漁期の駿河湾桜えびの秋漁。漁獲規制などを資源調査の結果を受けて決定する。
今年も桜えびがお手軽に食べられる状況にはならなそうですねぇ~。
2018年には春漁が不漁すぎて、秋漁が休漁にまで追い込まれるほど危機的な駿河湾の桜えび。
サクラエビは非常にレアな海洋資源で、駿河湾と台湾だけで水揚げされる。
一方の台湾南部の東港では1970年代にサクラエビが発見(というかサクラエビと認識)されて1975年から日本向けに干しサクラエビを出荷している。ここでは駿河湾より早く、2000年頃にピーク時に2000トン近かった水揚げが1/4の500トン程度まで落ち込む深刻な不漁に陥り、すぐに台湾政府は「MSY」という考え方を導入して、強力に資源保護に乗り出した。
「MSY」とは「最大持続生産量」のことで、対象となる魚種が将来的に漁獲高が最大になるよう資源管理を行った場合に逆算して現在の漁獲高を決めるもの。国際的には主流の考え方で資源管理のために漁獲高を制限する手法。一方日本では漁船数や漁法を制限するのが主流。2018年頃になってようやく導入を検討している。だが、2020年現在も資源調査対象の魚種を増やしてはいるものの、MSYを設定している魚種はない。
台湾が桜えび漁に対してMSYを導入した当初は、漁業者になかなか受け入れてもらえなかったという。まぁ、漁獲高をものすごく減らされるわけだから、漁師さんも困るよね。
しかし、このまま不漁が続けば桜えび漁自体の存続が難しい、という考えが徐々に広まり、受け入れられるようになったみたい。
現在もMSYによる管理を続ける台湾・東港、資源回復が進んだとみられ、以来不漁に見舞われていないようだ。しかし、最近になって漁獲高を伸ばしている台湾東北部・亀山島では資源管理が行われておらず、今後が懸念されている。
前述した通り、日本においてMSYは未だに設定されていないし、2024年くらいに沿岸魚種にMSY設定するかも、、、。と水産資源保護が遅れている。
現在、駿河湾で操業するサクラエビ漁船は、由比港と大井川港の2港に所属する約120隻。水揚げされるサクラエビの収益はすべての船に均等に分配される「プール制」という方式で乱獲を防ぎ資源保護を行ってきたし、漁師さんたちも保護できていると思っていた。
しかし感覚に頼った漁獲制限に留まったため、結果論としてサクラエビを保護することになっていなくて、現在の状況となってしまった。実際、秋漁が休漁になった2018年の前年秋には、0歳エビがほとんど獲れないという稚エビがいない状況があって、不漁の前兆があったのに気づくことができませんでした。
サクラエビが対象になるかもわかんない水産庁のMSY導入を待つんじゃなくて、抜本的に漁獲規制を総量規制なMSY方式にするとか考えないとヤバそうだよね。
 |
 |
 |
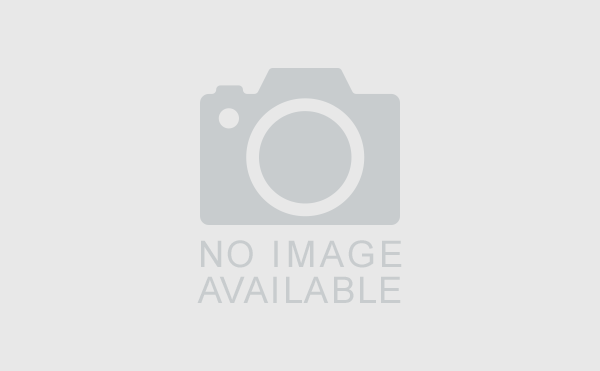
“サクラエビ秋漁 今年も不漁か” に対して2件のコメントがあります。